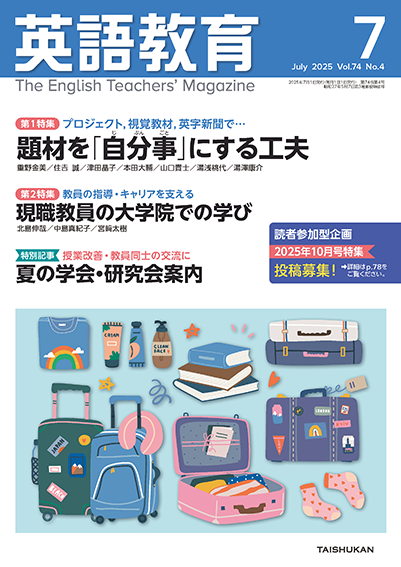
英語教育2025年7月号 大修館書店 July 2025 Vol.74 No.4
第1特集 プロジェクト、視覚教材、英字新聞で、題材を「自分ごと」にする工夫 第2特集 教員の指導・キャリアを支える 現職教員の大学院での学び
📘『生成AI活用術研究所 第16回』を読んで:教育の未来を切り拓くツールとしてのChatGPT
大修館書店の月刊誌『英語教育』(2025年4月号)の中から、特に興味深かった記事をご紹介します。
まずは、國學院大学の豊嶋正貴先生による【基礎編】「生成AI活用術研究所 第16回」。この回では、ChatGPTの基本的な機能――ファイルのアップロード、画像生成、Canvasによる文章編成、音声入力、音声モードの利用――についてわかりやすく解説されています。教育現場でのICT活用に悩む先生方にとって、「まずはここから始めてみよう」と思える安心のガイドです。
💬『SLAで答える指導のギモン 第4回』:ペアワークにおける日本語使用はアリか?
続いてご紹介するのは、宮城教育大学の鈴木渉先生による『SLAで答える指導のギモン』第4回。「ペアワークは同じ英語力同士で行った方がいい?」という問いに、第二言語習得(SLA)の視点から丁寧に答えています。
とりわけ印象に残ったのは、「ペアワーク中の日本語使用は必ずしも悪ではない」という点。英語力の低い学習者や年齢の低い学習者が安心して取り組むためには、日本語を部分的に使うことがむしろ効果的であるとのこと。「日本語禁止」ではなく、「どの場面で日本語を使うべきか」を子どもたちと一緒に考える授業設計の大切さに気づかされました。
🔍『英語教育研究のための研究倫理 第4回』:実験における「待機コントロール」という考え方
そして最後に、草薙邦弘先生(県立広島大学)と浦野研先生(北海学園大学)による『英語教育研究のための研究倫理』第4回。教育研究における“統制群”の扱い方について、「介入を行わない群」ではなく「介入の時期をずらす群(=待機コントロール群)」というアプローチを紹介しています。これは被験者への倫理的な配慮と教育的公平性の両立を図るもの。教育と研究の両立を考えるうえで、非常に学びの多い内容でした。
