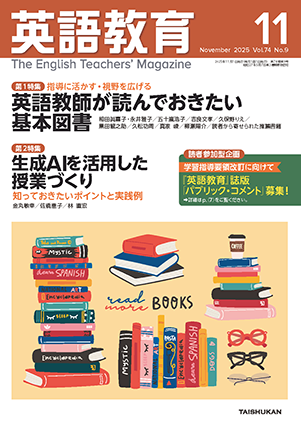
英語教育2025年11月号 The English Teachers’ Magazine November 2025 Vol. 74 No.9
第1特集 指導に活かす・視野を広げる 英語教師が読んでおきたい基本図書 第2特集生成AIを活用した授業づくり 知っておきたいポイントと実践例
AIを活用した授業づくり──知っておきたいポイントと実践例
1. イギリスの子どもたちはどうやって読み書きを学ぶのか
山下佳代子先生(第8回 イギリス・英語書き指導)
最初に興味深かったのが、イギリスの子どもたちの「Transcription(音声に沿った書き取り)」の指導法です。
子どもが “IS” を 発音記号 [ɪz] に従って “IZ” と書いても、教師は訂正しません。
まずは「音の通りに書くことを奨励する」段階を大切にしているからです。
その後、少しずつ正しい綴り(IS)を教えていきます。
スタンプ(大文字・period・スペース・phonics)は、
教師が子どもの書き取りを確認し、
「どの部分ができていて、何を意識すべきか」を共有するためのもの。
子どももそれを見て、自分が次に何を頑張ればいいのかが分かる仕組みです。
2. 生成AI活用術研究所 第20回「初級編:生成AIを学習に活用しよう」
豊島正隆先生(工学院大学教育開発推進機構 兼任講師)
今回特に注目したのは、ChatGPTに搭載されている「学習モード(Learning Mode)」。
通常のようにすぐに答えを提示するのではなく、
あえてヒントや問いかけを返すことで、
学習者自身に考えさせる仕組みになっています。
この“待つAI”の設計は、まさに主体的・対話的な学び(アクティブラーニング)そのもの。
教師のファシリテーションの感覚に近く、今後の授業デザインにも応用できそうです。
3. SLAで答える指導の疑問
「言語活動中心の授業では練習は不要?」
文法ドリルや音読練習は「実際のコミュニケーションとかけ離れている」と言われがちですが、SLA(第二言語習得)の立場では、むしろ練習こそが言語活動の土台であるとされています。
• 練習と活動の違い:
自分の考えや伝えたい内容があるかどうか。
• 分散学習のすすめ:
毎回少しずつ繰り返すことで、記憶が長期定着する。
• 練習の目的意識化:
「この練習はAという場面で自分の意見を言うため」と共有する。
練習はゴールではなく、言語活動で“使うため”の準備。
この視点を忘れないことが重要です。
4. 英文法解説の小技から
木原史隆先生(日本大学元教授・非常勤講師)
板書で進行形に線を引いたり、色を変えて強調しても、それだけでは理解は深まりません。
むしろ**「その文の次にどう続くか」**を示すことが教師の力量。
例:I’ve got my plane ticket.
→ この表現をどう“生かせる”かを2文で教える。
江川先生の言葉を借りれば「2 sentences 主義でいこう」です。
5. 推薦図書
• 『英語教師のための教育データ分析入門』
• 『SPSSでやさしく学ぶアンケート処理』
特に後者は、論文執筆や量的調査の基礎を固めるのに最適。
データ分析力が今後の授業研究の“武器”になりそうです。
6. AIを活用した授業デザイン実践例
「入試リーディングの指導をAIで個別最適化」
林直寛先生(京都府立峰山高校)
林先生の実践では、ChatGPTに以下のようなプロンプト設計を行っています。
🔹設定内容の概要
1. 役割:英語教師
2. 出題内容:大学入試共通テストレベルの読解問題を自動生成(400語以上)
3. ジャンル選択:パンフレット/議論/ブログ/物語/エッセイ/メール/論説文 など
4. 難易度選択:CEFR A1〜B1まで(選択肢の言い換え度で調整)
5. 出題数選択:ユーザーが選択
6. 回答後:正答・解説・語彙文法ポイントを日本語で提示、全文訳も表示
ポイント:正解の記号(A〜D)が偏らないように設定。
こうしたプロンプトを通して、生徒一人ひとりに最適な問題を生成できます。
7. 教員がAIアプリを自作できる!
「DIFY(ディファイ)」プラットフォーム
林先生は、AIアプリ開発プラットフォーム DIFY を用いて独自アプリを作成。
• 5つまで無料で作成可能
• 言語モデルの選択・API設定も柔軟
• 生徒はログイン不要でリンクをクリックするだけで利用開始
• 対話ログが保存され、学習履歴の振り返りも可能
DIFYの無料枠を使う場合は、API利用制限や規約を確認する必要がありますが、
教師が独自の教材AIを構築できるという点で非常に実践的なツールです。
🔗 DIFY公式サイトはこちら → https://dify.ai
📱 林先生のブログ「SETSブログ英語教員@AI活用術」にも実践記録が掲載されています。
まとめ:AI×英語教育の未来へ
AIが教師の代わりをするのではなく、学びの構造を支えるパートナーになる。
音声認識、読解生成、語彙フィードバックなど、多様な機能が生徒の“考える力”を支え始めています。
本号を読んで感じたのは、どの実践にも「人の学びを支援するAI」という一貫した思想があること。
AIは“答えを出す道具”ではなく、考えを引き出す鏡。
これからの授業デザインに、その思想をどう取り入れていくかが鍵になりそうです。
